俳句の切れって何?
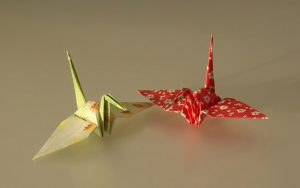
俳句には「切れ」というものがあります。
例えば
此道や行人なしに秋の暮 芭蕉
「このみちやゆくひとなしにあきのくれ」と読むのですが、これは
此道や
行人なしに秋の暮
という切れ方をしています。いわゆる『や』で切れているわけです。
どういうことかというと、此道(このみち)、つまり自分が歩いている道でしょう。そこでふぅっと息を抜く、一気に読まない。文章でいうと改行(場合によってはページをめくる)くらいの感じです。
そうすることで何が生まれるかと言うと余白です。意味の余白。そうすることで、その余白に様々な想像を入り込ませる事ができます。これがあるからこそ世界最短の詩として俳句が成り立っていると言っても過言ではありません。
でなければ、此道に行人なしに秋の暮で十分足りることでしょう。しかし、此道やとしたところに俳句の良さがあります。
俳句は短いので一回読み終えてから、もう一度最初に戻りますよね?
俳句は短いから何度か読むと思います。行く人もいない秋の暮。それが自分の歩むこの道なのだ。と「此道」へ返ってきます。途方もない侘しさや徒労感、いろいろな思いが「此道」に入ってゆくような感じがしませんか?だからこそ「此道や」としたのです。
切れの話はなかなか難しいのですが、切れた部分に詠嘆の入る余白があるというように覚えておいていいと思います。特に「や」は強い詠嘆を意味します。
ただ、
寒卵わが晩年も母が欲し 野澤節子
のように、「や」が入っていない「切れ」もあります。こういう場合はどう見るかというと、意味が通るかどうかを判断します。この句の場合、寒卵とそれ以降に意味の繋がりはありませんよね。
だから
寒卵
わが晩年も母が欲し
のようなイメージになります。つまり「ここに一個の寒卵がある。(余白。改行)自分の晩年にも母がいて欲しいものだなぁ」というようなことになります。
どうして寒卵なのか。寒い時期の卵というのは滋養があるされていますから、家庭のあたたかさを思い出させてくれますよね。寒い中にパカっと割った卵の黄身はなんとなく温もりを感じさせます。さらに、卵というのは当然雌鳥から生まれますから誕生にもつながるイメージです。
晩年になっても母が生きていて欲しい。もう一度母の温もりが欲しい。という作者の言葉に響いてきます。
このように、目には見えない切れもあります。
切れは別に五七五のどの位置に来てもよく、もっと言えば、七の途中で切れても構いません。
上の五の後、あるいは下の五の前で切るのが基本形ですので最初はそこで切るようにして俳句を作ると良いと思います。
いへばたゞそれだけのこと柳散る 久保田万太郎
文語ですからちょっとわかりやすくしますと、
言えばただそれだけのこと
柳散る
下五の前で切れている例です。「言ってしまえばそれだけのことだ。(余白。改行)目の前では柳が散っている」柳はほろほろとこぼれるように散っていくのが特徴ですから、なにか寂しい事柄を胸に秘めているのでしょうか。
これも意味の繋がりで「切れ」を見極める例です。
切れのない俳句もある
切れのないような俳句もあります。
初蝶の遠きところを過ぎつつあり 山口誓子
この句では句の途中で切れは見当たりません。意味はまっすぐ通っています。
「初蝶(その年の春に初めて見た蝶のこと)が遠いところを過ぎていくところだ。」という句ですが、切れがありません。別にこれはこれでありなのです。
切れがあったほうが俳句的なのですが、わざと切れを作らずに一気に読ませる。つまり、散文の抜き出しのような形にして印象を強くするという手法です。
そのためにはその一文が印象的でなくてはなりません。
鳥の巣に鳥が入つてゆくところ 波多野爽波
これも同様の切れがない句ですが、当たり前のことを言いつつ印象的ですよね。
こういう切れのない句の場合、切れはその句全体にわたると言われます。
(余白)
鳥の巣に鳥が入つてゆくところ
(余白)
のようなことです。抜き出された場面の前後に余白が生まれてるイメージです。
とらへたる蝶の足がきのにほひかな 中村草田男
最後が「かな」や「けり」で終わる句に多いのはそのせいです。「切れ」というのは詠嘆を生む部分です。「かな」や「けり」の後は(詠嘆・余韻)ということですから、最後で切れているということでいいのです。
まとめると
俳句には切れがある。
それは詠嘆を産んだり、余韻を生んだりする。
「切れ」は句の途中のことが多いが、句の最後にくることもある。
ちょっと難しいですが、多くの俳句に親しんでいくと自然にわかるようになってきますので、まずは色んな俳句に触れてみてくだい。
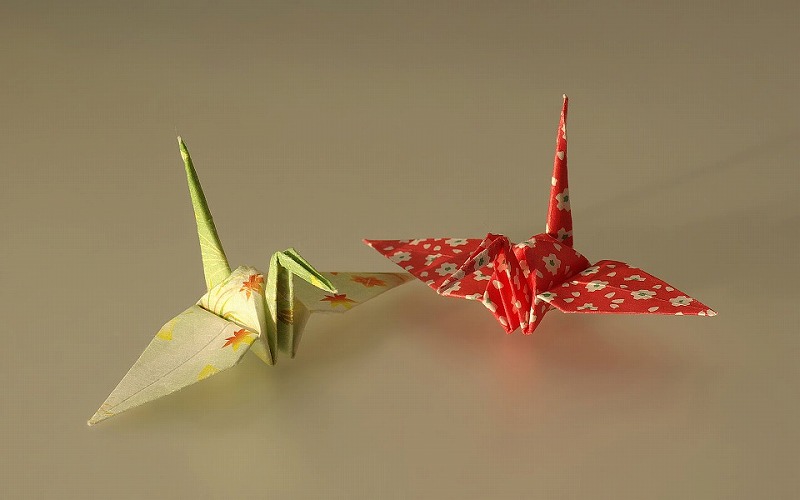


[…] ※「切れ」とは何かはこちらの記事を […]